学びの特徴
- 01“生きた福祉”を学び実践力を養う
- 02可能性を広げる自由な履修制度
- 03卒業後は福祉職として活躍
01“生きた福祉”を学び実践力を養う
目標は福祉領域の法制度、サービスに関する知識を活用しながら、支援を必要とする人に寄り添い、生活問題の解決を図るソーシャルワーカーを育成することです。そのため、現場での実習機会を数多く設けています。さらに、豊富な実務経験を持つ教員から“生きた福祉”を学ぶことで実践力を養っていきます。
02可能性を広げる自由な履修制度
必修科目を少なめに設定し、学生自身が興味のある分野を選択して学ぶ独自の履修制度を設けています。これが、社会福祉士として幅広い知識と高度な専門性を身につけることにつながり、将来の活躍の場も大きく広がります。さらに花園大学では、他学科の専門科目も履修できるようになっています。
03卒業後は福祉職として活躍
花園大学には60年以上の社会福祉教育の歴史があり、卒業生の多くが福祉を支える担い手として全国で活躍しています。これは先輩たちの実践力の証であり、その信頼が良好な就職状況を支えています。
将来を拓く3つのコース
ソーシャルワークコース
以下の資格を取得し、社会福祉実践の専門職を目指します
社会福祉士国家試験 受験資格
精神保健福祉士 受験資格
上記のほかにも他学科受講により資格・免許が取得できる場合があります。
社会福祉実践と資格注 赤文字で表記した資格が本学科で取得できます。

- 現場に強い実践力の育成:“生きた福祉”を学び実践感覚(ノウハウ)を養う
- 国家試験合格に向けたバックアップ体制
- 学内教員による対策講座の実施!!

こども未来コース
虐待・いじめ・不登校・貧困など、生きづらさを抱えたこどもたちが存在します。
また、様々な障がいのあるこどもたちの学習権の保障、合理的配慮の必要性が指摘されています。
こども未来コースでは、こどもの最善の利益に基づいた個々のニーズに応じた支援の在り方を学びます。
スクールソーシャルワーカーとは?
スクールソーシャルワーカーとは、学校という場で活動する福祉の専門家です。チーム学校として、いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待などの子どもたちを取り巻く問題に、教師、カウンセラーなどとともにチームで課題の解決にあたります。スクールソーシャルワーカーは、(社)日本ソーシャルワーク教育学校連盟の認定資格で、社会福祉士あるいは精神保健福祉士の資格を取得していることが認定の条件となります。
スクールソーシャルワーカーについて
(クリックダウンロード)

地域貢献コース
「地域に出会い、地域に学ぶ」がコンセプト
地域を知り、地域の課題を発見し、住民との関わりを通じて課題解決を図る経験値・実践知を養います。
こんな方にオススメです!
- 地域福祉やまちづくりに関心がある(将来、そんな仕事に就きたい)
- 行政やNPOのプロジェクトや、地域活動に関わってみたい

- 京都や地元で地域課題の解決を目指したい
- 社会福祉法人等において、ボランティアに関する仕事がしたい

地域貢献コース紹介パンフレット
(クリックダウンロード)


4年間の学び
-
- 1年生
社会福祉の基礎を学び実践の土台を固める
-
1年生では、「社会福祉の原理と政策」「社会福祉史」「ソーシャルワークの基盤と専門職」の 必修科目の履修を通じて社会福祉の基礎を学びます。「社会福祉とは何か」を知るとともに、 支援対象者の現状を深く理解し、具体的な支援につなげる実践力の土台をつくります。
- 1年生
-
- 2年生
実践に向けた応用を学び支援の基礎力を養う
-
2年生では、社会福祉士資格取得に直結する「ソーシャルワーク実践」や「地域福祉と包括的支援体制」を履修し、1年生で履修した基礎科目での学びを応用・発展させます。また、多様な福祉現場の専門職をゲストスピーカーに招いて援助の在り方を考え、実践に向けた支援の基礎力を養います。
- 2年生
-
- 3年生
学びをゼミで深めつつ実習の現場で自分を試す
-
3年生では、社会福祉に関する自身の興味・関心にあわせ、専門性を持つ教員のもとで学びを深める「社会福祉学演習 A」(ゼミ)が始まります。あわせて社会福祉士・精神保健福祉士としての実践に不可欠な「ソーシャルワーク実習」などに取り組み、自身の力量を現場実践で高めていきます。
- 3年生
-
- 4年生
学びの集大成に取り組み国家試験合格につなげる
-
4年生では、ゼミで自身の研究テーマを定め、研究成果を卒業論文にまとめます。あわせてソーシャルワークを専門的かつ実践的に学修するとともに、国家試験対策に専念し、社会福祉士・精神保健福祉士の資格取得の目標を達成します。
- 4年生
ピックアップ授業
-

フィールドワーク実習
地域課題や社会的課題の解決に実践的に取り組む主体(地域住民組織、NPO、行政など)の活動に主体的に関わりながら、「地域に学び、地域を知る」ことを目指します。
-

スクールソーシャルワーク実習指導
小・中学校や教育委員会での実習を通して、教育現場や地域における児童生徒の現状を把握。スクールソーシャルワーカーとしての役割やあるべき姿について学びます。
動画コーナー
YouTube
-
社会福祉学科 学科紹介(2021年度)
-
社会福祉学科 模擬授業(2020年度)
-
神部先生
-
早川先生
-
深川先生
卒業論文のテーマ・研究テーマ
- 介護職員の職業性ストレスに対するメンタルヘルスケア
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護における訪問介護員のストレス対処について
- 不登校支援の課題と展望―不登校当事者の視点に着目して
- 子ども食堂に関わるボランティアスタッフの参加動機と継続理由
- 高齢者の介護予防への取り組みに関する文献的検討
- 高齢者が活躍できる社会の実現に向けての課題と展望
- 災害時における障害を有する方への支援と対策
- 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」成立をめぐって
卒業後の進路

卒業後の主な進路
社会福祉施設・機関(こども・高齢・障害・地域)、病院(医療ソーシャルワーカー)、学校(スクールソーシャルワーカー)、公務員(福祉職・警察・消防等含む)、一般企業/大学院進学 など
就職実績
社会福祉法人清和園 社会福祉法人京都老人福祉協会 洛和会ヘルスケアシステム 社会福祉法人南山城学園 社会福祉法人京都福祉サービス協会 社会福祉法人青葉学園 本願寺ウィスタリアガーデン 社会福祉法人京都会社事業財団 京都厚生園
公益財団法人豊郷病院 社会福祉法人愛仁会リハビリテーション病院 医療法人芙蓉会 社会医療法人若弘会若草第一病院 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 増田医科器械
京都市社会福祉協議会
大津市消防
三重スバル自動車株式会社 株式会社ヤサカ/湖光グループ 株式会社エリッツ KDDI Sonic-Falcon株式会社 株式会社ライフコーポレーション 株式会社LITALICO





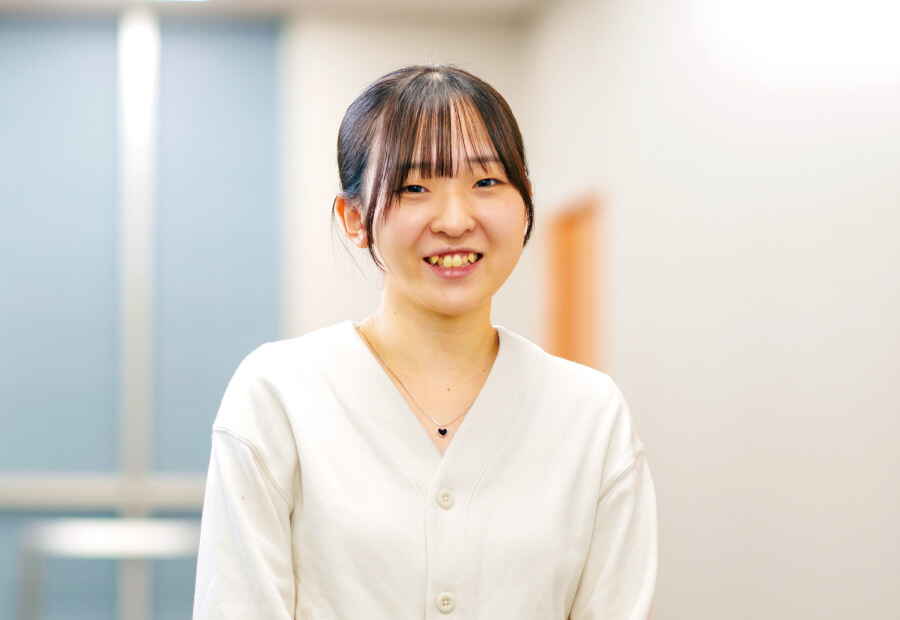

社会福祉学科とは社会福祉士の資格取得に向け理論と実践を学ぶ
社会福祉について深く学び、政策・法律・制度の知識とともに、相談業務などの実践力を身につけていく学科です。福祉の現場で指導的な立場にいる卒業生とのパイプを活かした実習ができるのも魅力です。
社会福祉学科の特長は、その実践力にあります。生きづらさを抱えるこどもや介護を必要とする高齢者、様々な障がいを抱える方、貧困に陥っている方など、生きていく上で何らかの課題のある人々のくらしについて考えます。
現代社会における多様かつ複雑な福祉的課題の現状を理解し、その課題解決に向けて必要となるノウハウについて学びます。